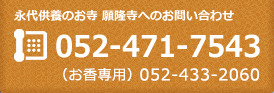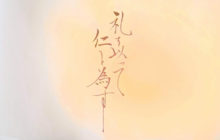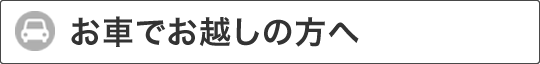平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
日頃ご参詣いただく皆様のご支援のおかげで、
風雨で剥げ落ちていた手水舎の塗装の塗替えをすることができました。
感謝とともに、ここにご報告させていただきます。
手水の主な目的は、心身を清めること。心を落ち着かせ、お詣りください。
願隆寺
住職 石濵 章友
<施工前>
<施...
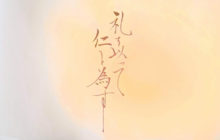
【円純庵と共に〜仁学書院の道】
昔は子供も大人も学んでいた心の学問 戦後、学校や家庭から学ぶ機会がどんどん消えてなくなりました。 それにより生きづらい世の中となり、複雑な問題も増えて参りました。 日本人が強くある為に必要な仁義道徳の学問は、これまでも数々の偉人達が学ばれてきた学問です。
2024年度前半には、日本に儒教を広めた渋沢栄一さんに一万円札が実に40年ぶりの人物変更となります。...

~重陽の節供飾り「茱萸嚢(しゅゆのう)」を作ろう!~
1月1日、3月3日、5月5日など、奇数(陽数)が重なる日は縁起が良い日として、祝われてきましたが、その陽数が最も大きくなる日が9月9日です。
...
願隆寺がお世話になっている大阿闍梨様をお招きし、重陽の節会を行います。
今日に至るまで日本で伝承されている五節句とは、江戸時代に幕府が制定した五つの節日(せつにち)をさします。節日そのものは奈良時代より定められていましたが、それらは主として宮中儀礼としての宴であり、史料をひもとくと「節会(せちえ)」とも記されています。
また、「節句(せっく)」は元来「節供(せっく)」という漢字が当てら...

6月の手作りお香講座は、お部屋いっぱいに香りひろがる「お部屋香」作りです。
お部屋香とは香原料を詰めてお部屋用にした大きな匂い袋のようなお香です。お部屋いっぱいに香りがひろがるように香原料を調合して作ります。
平安時代から暮らしの中で親しまれるようになったお香。お部屋香は現代でいうところの「ルームフレグランス」です。
お香はもともと邪気を払い、場を浄化してくれるもの。リラ...

【 願隆寺 和文化講座 お寺で新やまと文字®︎ 】
本講座では月の満ち欠けと太陽の周期、即ち旧暦を大切に取り入れ、季節の行事や文化を学びながら、旬の言葉、昔からある使わなくなってしまった美しい言霊を綴ります。
月に一度、約2時間のレッスンで、本科基礎クラス1年、上級者1年以上でインストラクターの資格を取得していただくことも可能です。インストラクターを目指す方と、...

願隆寺で大変人気の新やまと文字講座とお香(薫物)作りのコラボ講座です。
まず前半は、新やまと文字の生みの親であるデザイン書作家の詠月先生から、和文化のお話と新やまと文字の基本を学んでいただいたあとに、今回作っていただくお香の銘「侍従・黒方」を書いていただきます(イベントの写真は「菊花」の写真になっていますが、今回は侍従・黒方のデザイン書になります)。
そして後半は、平安時代...

本講座では月の満ち欠けと太陽の周期、即ち旧暦を大切に取り入れ、季節の行事や文化を学びながら、旬の言葉、昔からある使わなくなってしまった美しい言霊を綴ります。
月に一度、約2時間のレッスンで、本科基礎クラス1年、上級者1年以上でインストラクターの資格を取得していただくことも可能です。インストラクターを目指す方と、趣味で気軽に楽しむ方とに分かれます。
現在、20代の方から9...

自分のために、家族のために
『もしもノート』を活用される方が増えています。
・もしも、財布を落としてしまったら
・もしも、家族が入院してしまったら
・もしも、身近な人が急に亡くなってしまったら
・もしも、急に家を継ぐことになったら
入院時や相続時など、さまざまな「もしもの時」に役立つのが『もしもノート』です。
大切なことを大切な人へ、『もしもノート』に書き記しておくことで...